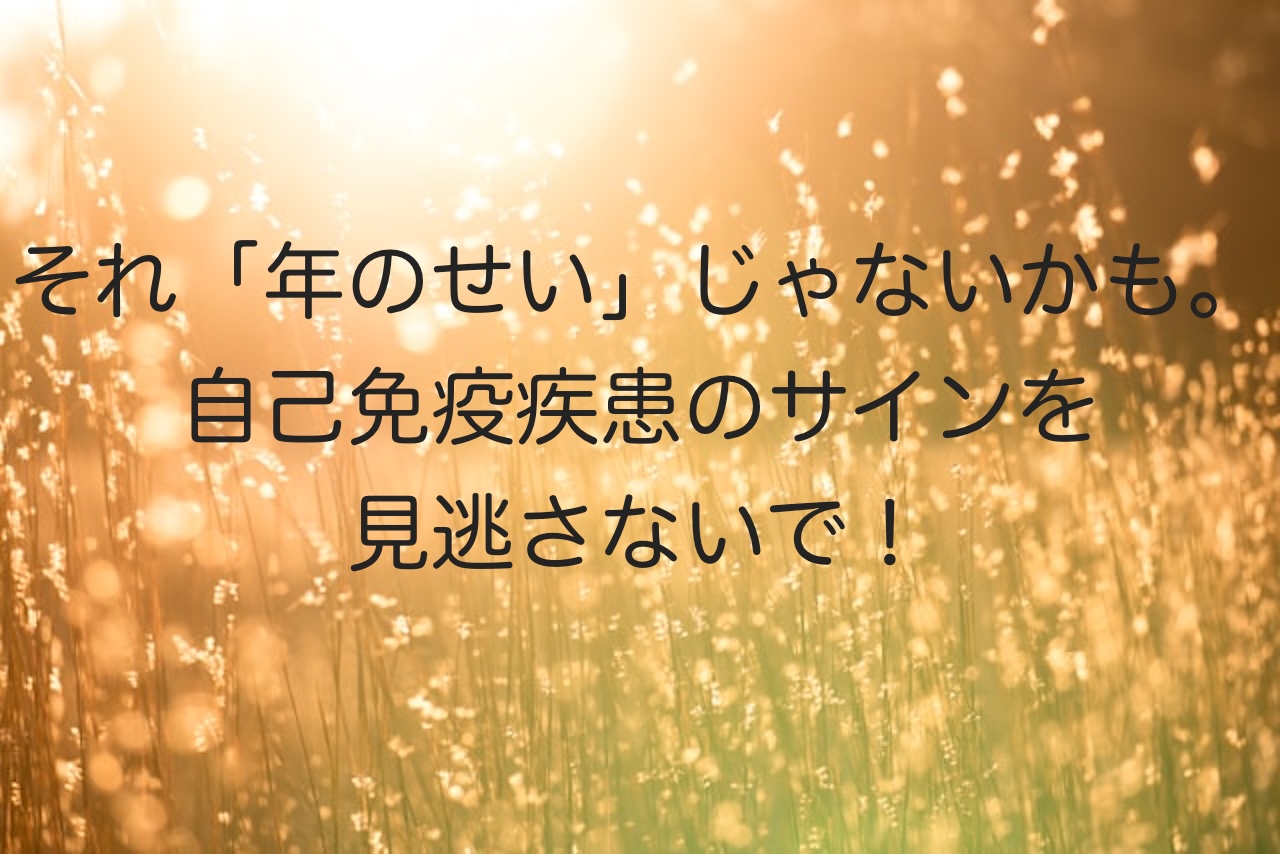あなたの体の乾燥、単なる「年のせい」や「疲れ」で片付けていませんか?
最近、こんな症状が続いていませんか?
- 「いつも喉が渇いている気がする」
- 「目がゴロゴロして、コンタクトが痛い」
- 「口の中がネバネバする、話しにくい」
これらは、もしかしたら自己免疫疾患である「シェーグレン症候群」の初期サインかもしれません。特に40代以降の女性に多く見られます。単なる「乾燥」と見過ごさず、あなたの体からのサインに耳を傾けましょう。
シェーグレン症候群は、早期に適切な治療を開始しないと、「乾燥」だけでは終わらない全身性の病気です。あなたの体内で静かに進行しているかもしれない炎症に、今すぐ目を向けましょう。
🚨 潜在的な患者さんが自覚しやすい「初期サイン」のチェック
以下の症状は、体内の免疫細胞が涙腺や唾液腺などの外分泌腺を攻撃し始めている兆候です。
1. 口腔内のサイン(ドライマウス)
ただの喉の渇きではなく、唾液の質の変化に注目してください。
- ネバつきと会話の困難さ: 口腔内が水っぽくなく、粘り気のある唾液しか出ないため、長時間の会話や歌唱が困難になる。
- 食事中の頻繁な飲水: 特にパンやクッキーなどの乾いた食品が飲み込みにくく、一口ごとに水を必要とする。
- 口腔内の深刻なトラブル: 唾液に含まれる抗菌成分(リゾチームなど)が減るため、短期間で多発する虫歯(特に歯の根元)や、治りにくい口内炎が頻繁に発生する。
2. 眼のサイン(ドライアイ)
眼の乾燥は、角膜(黒目)の表面の細胞が傷ついている証拠かもしれません。
- 持続的な異物感: 目を開けている限り、砂やゴミが入っているようなゴロゴロ感やヒリヒリ感が続く。
- 涙の質と量の低下: 悲しい時でも涙が出にくい、または、涙が出てもすぐに乾いてしまう。
- まぶしさ(羞明): 角膜の傷により、光に過敏になり、太陽光や蛍光灯がやけにまぶしく感じる。
3. 予想外の全身サイン
乾燥症状に加えて、免疫の異常が原因で全身に炎症が及ぶことで、以下の症状が出ることがあります。
- 疲労・倦怠感: ぐっすり寝ても取れない、原因不明の強い全身倦怠感が続く。
- 関節の痛み: 朝起きた時に関節がこわばる、または、特定の関節に腫れを伴わない痛みが移動する(多発関節痛)。
- 皮膚症状: 下肢に赤紫色の斑点や点状出血(紫斑)が出たり、皮フが極度に乾燥し、かゆみを伴う湿疹が出たりする。
4. 私のケース
私はどんなことがあったか振り返ると、とるに足らないと放置していた症状がたくさん出ていました。
- 肌荒れ:何年も腰やお尻にニキビがたくさんできていました。飛行機や新幹線にたくさんのっていることやストッキングのせいだろうと思っていました。振り返ればリーキーガットの症状、もしくは乾燥していた結果だったのかと思います。
- 手荒れ、手湿疹:指にもかゆいブツブツが1、2年出ていました。指に虫がわく夢を見るほどかゆい時もありましたが、これも体内で炎症が進んでいたんだと思います。何度皮膚科で薬を処方してもらって一時的におさめても何度も再発していました。
- 膝の痛み:本格的に肩の痛みが出る前に、膝関節の痛みが出たりしていました。当時は運動不足かな?年齢も年齢だし運動しないとな、と思いっていた程度でたいして気にもしていませんでした。
私はたくさん皮膚を中心に症状が現れていましたが、気にも留めていませんでした。
🔬 早期受診が未来を変える:病院で受ける検査とは?
これらの症状が当てはまっても、「気のせいかも」と受診をためらわないでください。シェーグレン症候群は、比較的簡単な検査で診断の手がかりを得ることができます。
- 血液検査:
- 抗SS-A抗体 / 抗SS-B抗体: シェーグレン症候群に特徴的な自己抗体です。陽性であれば強く疑われます。
- リウマトイド因子: 陽性になることもあり、他の膠原病との合併も確認できます。
- 眼科検査(シルマーテスト):
- 目盛りのついた紙をまぶたの端に挟み、5分間で涙がどれだけ染み込むかを測定し、涙の分泌量を評価します。
- 耳鼻咽喉科・歯科口腔外科検査(ガムテストなど):
- ガムを噛んでもらい、10分間での唾液の量を測定し、唾液の分泌量を評価します。
📣 気になったら、専門医に「検査を希望する」と伝えてください
もしチェックリストに複数当てはまる場合は、自己判断で市販薬に頼るのをやめ、「リウマチ・膠原病内科」、または「口腔外科」や専門的な「眼科」を受診しましょう。
医師に「シェーグレン症候群の疑いがあるので、抗SS-A/SS-B抗体の血液検査とシルマーテストを希望します」と伝えることが、スムーズな診断への近道です。
早期に病気をキャッチし、適切な治療(人工涙液や唾液分泌促進薬など)で症状をコントロールすることが、あなたの健康な生活を守る最善の方法です。
検査したとて治る病気ではありませんので、併せて食事療法やストレスの緩和など、このブログでご紹介している作戦もぜひ取り入れてくださいね!
この記事が不安を感じている方の一助になれば幸いです。